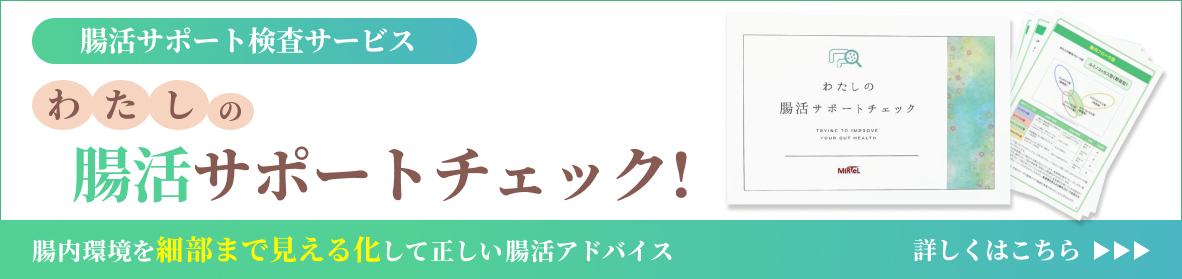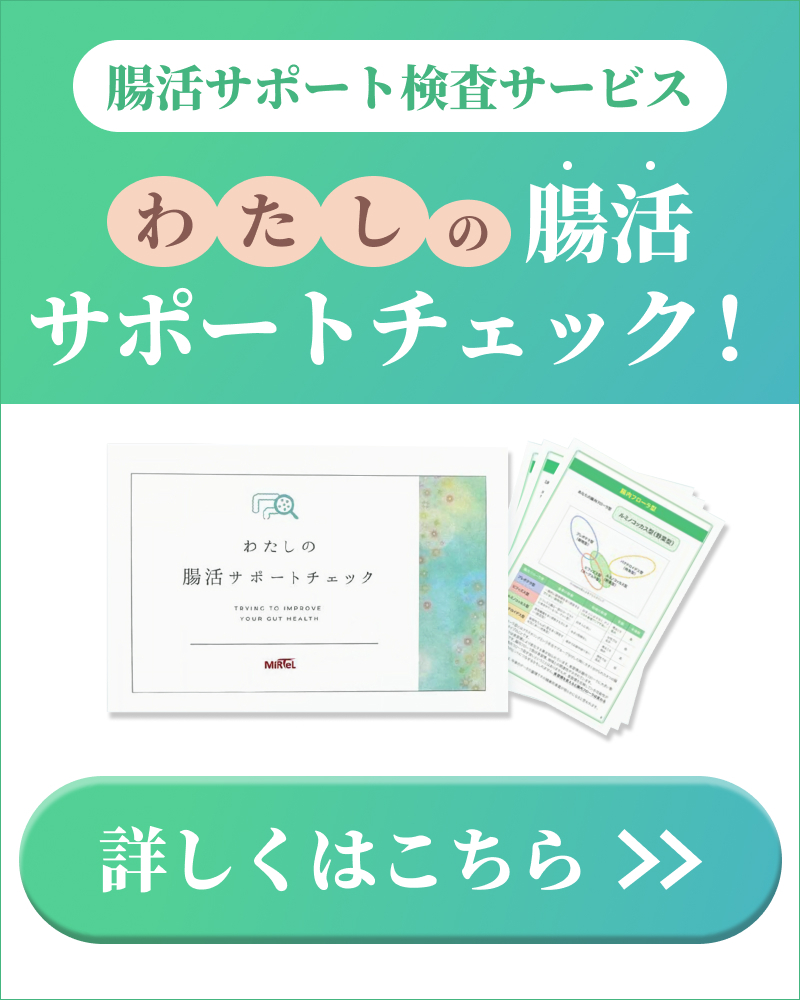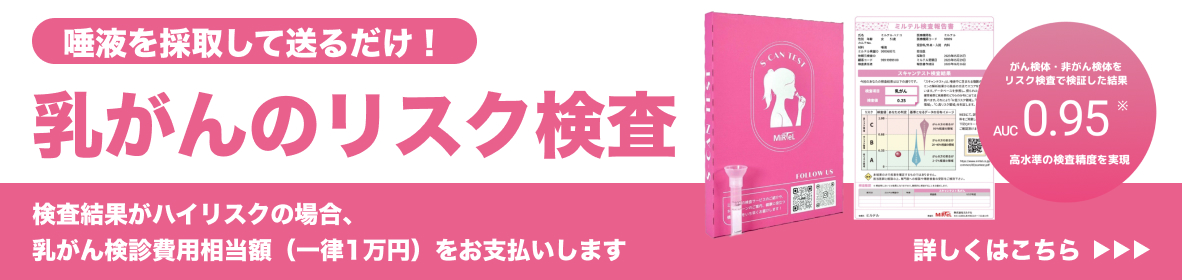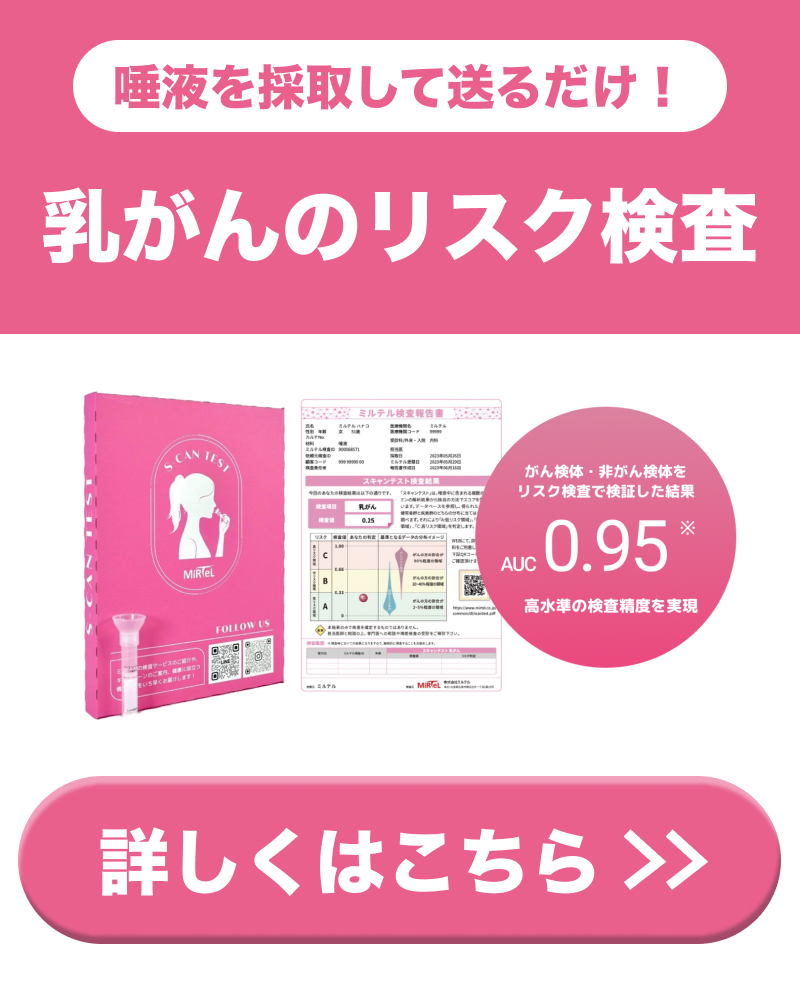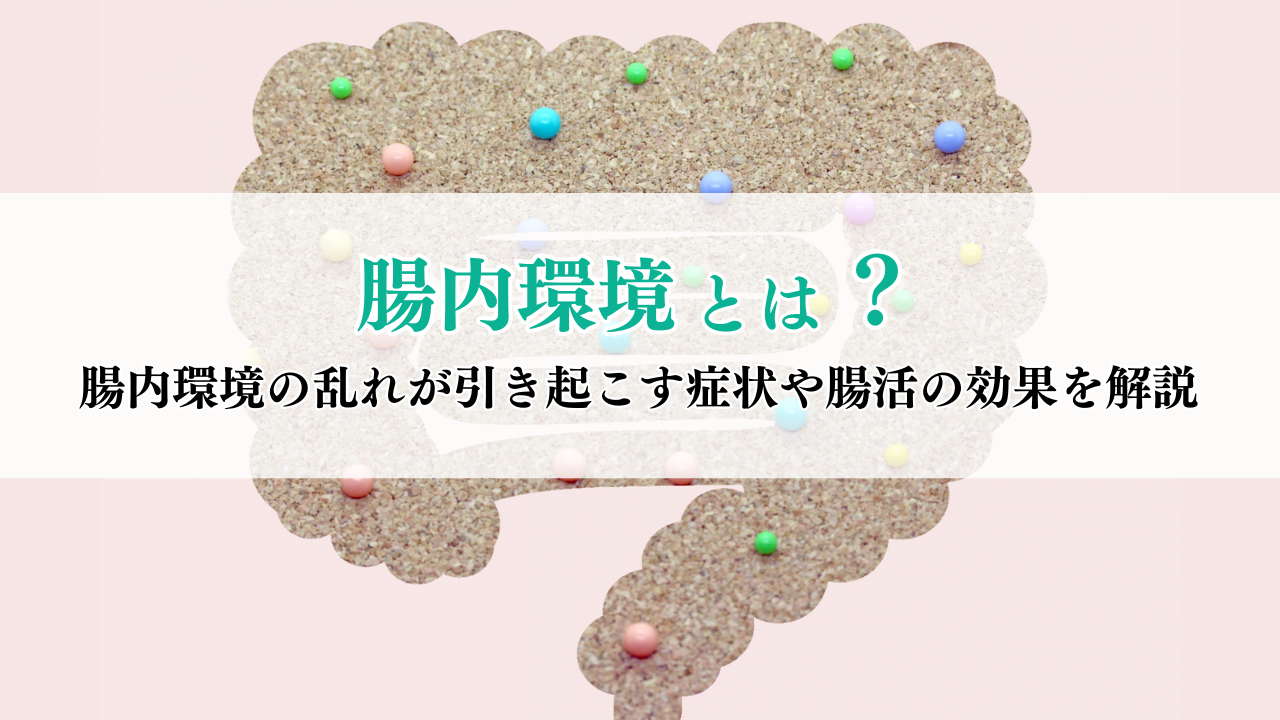
腸内環境とは?腸内環境の乱れが引き起こす症状や腸活の効果を解説
関連キーワード
腸活
腸内環境とは腸の環境全体のことで、内部の細菌バランスが乱れると心身の健康に悪影響を及ぼします。
本記事では、腸内環境の良し悪しを決める要素や、腸内環境の乱れによって引き起こされる諸症状を解説します。
腸内環境の良し悪しは腸内細菌のバランスにより決まる
腸内環境は腸内部の環境全体を意味します。腸内環境の良し悪しを決定する要因は、腸内細菌のバランスです。
腸内には40兆個の腸内細菌が存在し、花畑のように分布して見えることから「腸内フローラ」と呼ばれます。腸内細菌を含んだ腸内環境は人それぞれ異なり、食事や運動といった生活習慣でも変化します。
腸内環境と腸内細菌について、以下の2点を説明します。
- 腸内細菌は大きく3種類に分けられる
- 有用菌(善玉菌)が優勢だと腸内環境が整う
また、腸内フローラについては、以下のページで詳細に説明しているので、ぜひ参考にご覧ください。
関連記事:腸内フローラの正体は?理想のバランス、免疫やメンタルに影響する役割についても解説
腸内細菌は大きく3種類に分けられる
腸内細菌は大きく以下の3種類に分けられます。
各腸内細菌の役割は以下の通りです。
| 腸内細菌 | 働き・役割 |
|---|---|
| 有用菌 (善玉菌) |
・有害菌の増殖を抑える ・ビタミン類(ビタミンB6や葉酸など)の生成 ・腸のぜん動運動を促す ・病原菌の増殖を抑える |
| 有害菌 (悪玉菌) |
・有害物質を産生する ・ガスを発生させる ・腸の動きを低下させる |
| 日和見菌 | 有用菌と有害菌のうち腸内で高い割合を占める菌と同じ働きをする |
腸内細菌はそれぞれがバランスをとって共存しており、理想的な腸内細菌の割合は「有用菌:有害菌:日和見菌=2:1:7」です。
腸内細菌のバランスが取れると、腸内環境が整い健康な状態を維持しやすくなります。逆にバランスが崩れると、心身の不調や病気の原因となるのです。
関連記事:腸活とは?腸内環境を整えるメリットと実践方法を解説!
有用菌(善玉菌)が優勢だと腸内環境が整う
腸内の有用菌が有害菌よりも優勢だと、腸内環境が整っている状態といえます。
逆に有害菌が増えると、腸だけでなく全身の健康状態に悪影響を及ぼすため注意が必要です。
腸内細菌のバランスが崩れる原因の例として以下が挙げられます。
- 偏った食生活
- 運動不足
- 睡眠不足
- 慢性的なストレス
- 抗生物質の使用
乱れた腸内環境を整えるためには、食物繊維が豊富な食品を取り入れる・生活リズムを整えるなどを行い、有用菌が有害菌よりも優勢な状態を作ることが大切です。
有用菌のはたらきや増やし方について、以下のページで詳細を説明しているので、ぜひ参考としてご覧ください。
関連記事:有用菌(善玉菌)とは? 種類やはたらきから増やし方まで詳しく知ろう
腸内環境が乱れが心身の不調や病気を引き起こす
腸内環境の乱れが引き起こす心身の不調や病気の例として、次の4つを紹介します。
- 便秘や腹痛
- 肌荒れ
- 免疫機能の低下
- 糖尿病やがんなどの病気
便秘や腹痛
腸内環境の乱れは、便秘や下痢、腹痛などの症状を引き起こします。
腸内環境が乱れると腸のぜん動運動が円滑に行われなくなります。ぜん動運動※が鈍くなると排便しにくく、便秘になりやすいです。さらに、便秘によって有害菌が増え、作り出したガスが腸内に溜まることで、腹部膨満感や腹痛を生じる場合があります。
逆に腸のぜん動運動が過剰もしくは消化不良を起こすことで、下痢になることもあります。
※ぜん動運動:腸の内容物を運ぶために行われる腸管の伸縮運動
関連記事:便秘の解消法は?腸内環境を改善する食べ物やマッサージを解説
肌荒れ
腸内環境が乱れると、肌荒れが生じやすいです。
腸内細菌のバランスが崩れると、有害菌が作り出したアンモニアやリポ多糖(LPS)などの有害物質が腸管から血液に吸収されます。有害物質が血管を通して全身に運ばれ、皮膚から排出されることで肌のトラブルが引き起こされるのです。
特に腸内環境の乱れによる便秘症状が続くと、血液中の有害物質が増えます。
つまり、腸内環境を整えて有害菌の増殖を抑えれば、皮膚の状態を改善できる可能性があるでしょう。
免疫機能の低下
腸内環境の乱れは、免疫機能の低下を引き起こす場合があります。
腸には腸管免疫と呼ばれる、体内へ侵入した病原体や有害物質から身体を守る仕組みがあります。
しかし、腸内細菌のバランスが崩れると腸管免疫の機能が低下するため、感染症やアレルギーのリスクが高まる可能性があるのです。
体全体で機能している免疫細胞の約6~7割は腸に集まっています。つまり、全身の免疫機能に影響しやすい腸内環境を整えることが重要と言えるでしょう。
糖尿病やがんなどの病気
糖尿病やがんなどの病気も腸内環境の悪化で引き起こされる可能性があります。腸内細菌が作り出す、短鎖脂肪酸(酢酸や酪酸など)が減少するためです。
短鎖脂肪酸には、免疫機能をサポートするだけでなく、腸内を弱酸性にして有害菌の増殖を抑え、病気のリスクを下げる働きがあります。
さらに、短鎖脂肪酸は血糖値を一定に保つ働きを担うホルモンである「インスリン」の分泌促進や脂質代謝の改善に寄与する働きもあります。そのため、短鎖脂肪酸が減少すると、肥満や糖尿病の発症リスクに影響があると言えるわけです。
腸内環境を整える腸活で不調を改善
腸内環境を整える腸活に期待できる効果は、次の3つです。
- 便通改善でお腹がスッキリする
- 美肌・ダイエット効果で外見が変わる
- 精神的に安定する
便通改善でお腹がスッキリする
腸活に取り組むと、便通改善によりお腹をスッキリさせる効果が期待できます。
腸活により腸内の有用菌が優勢になれば、腸の活動が促進されて排便がスムーズになります。また、便秘解消以外に下痢や腹痛の改善にも腸活はおすすめです。
便通改善を目的として腸活に取り組む際は、有用菌を増やす効果や便のかさを増して排便を促す効果がある食物繊維を積極的に摂取しましょう。
食物繊維の食事への取り入れ方やオススメの食品は以下のページで詳しく解説しているので、参考にご覧ください。
関連記事:便秘解消に効果的な食物繊維の取り入れ方とおすすめ食品
美肌・ダイエット効果で外見が変わる
腸内環境を整える腸活は、美肌やダイエット効果も期待できます。
腸活により有害菌の増殖を抑えられれば、肌荒れの原因となるアンモニアやリポ多糖(LPS)といった物質の発生を減らせるためです。
さらに、腸活で有用菌を増やせば、脂質代謝の向上やインスリンの分泌促進をする短鎖脂肪酸を増やせます。腸内で短鎖脂肪酸が増えれば、効率的にダイエットを進められるでしょう。
美肌やダイエット効果を目的としても、腸内環境を整える腸活はおすすめです。
関連記事:腸活でダイエット!成功につながる5つの理由や注意点も解説
精神的に安定する
腸活はメンタルの安定の効果も期待できます。
腸と脳は「脳腸相関」と呼ばれる関係にあり、互いに影響しあっています。ストレスを感じた際に、腹痛や下痢を引き起こす「過敏性腸症候群」は脳と腸が影響しあっている事例です。
逆に腸内環境を整えると、ストレス緩和や精神の安定が見込めます。実際に腸内の有用菌を補うプロバイオティクスによって、不安や抑うつの程度が低下したという研究結果があります。
腸と脳の関係についての詳細は以下のページで説明しているので、参考にご覧ください。
関連記事:腸が「第二の脳」と呼ばれるのはなぜ?整腸とメンタルヘルスの関係を解説
有用菌を増やす生活習慣を取り入れ腸内環境を整えよう
腸内環境を整えるには、有用菌を増やす習慣を組み込んで生活を改善する「腸活」がおすすめです。
腸活の具体的な方法は次の通りです。
- 有用菌を補い、増やす食生活を取り入れる
- 適度に運動する
- 生活リズムを整える
具体的な食生活の改善方法や運動の方法は以下のページで説明しているので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:腸活の簡単なやり方は?忙しい人でもすぐに取り入れられる6つの方法
関連記事:腸に良い運動が便秘解消のカギ!手軽にできるエクササイズを紹介
腸内環境を整えるにはセルフチェックや経過観察も重要
腸内環境は腸内細菌を含めた腸内全体の環境を指します。腸内環境の改善には、腸内の有用菌を増やすことが重要です。
腸活で有用な腸内細菌を増やすには、食事や運動といった生活習慣を改善する必要があります。また、効果がみられるまで、2週間程度を目安に継続的な腸活が必要です。
腸活の成果は便通の状態でも確認できますが、より細かく状況を調べたい場合は、ミルテルの「わたしの腸活サポートチェック」の利用をおすすめします。
自身の腸内環境を的確に把握した上で、より効果的な腸活に取り組み、心身の健康を目指しましょう。